おしらせ
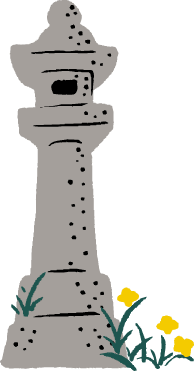
一本の木から絵馬ができるまで③

ざっくりと製材した木材を次は仕上げていきます。
お願いするのは「中嶋木工所」さん。神社で木の加工品が必要な際は必ずお世話になる大村の職人さんです。とびきり器用で、どんなお願いも簡単なイメージをお伝えするだけで、こちらの想像以上の製品に仕上げてきて下さいます。そんな中嶋木工さんにお仕事をお願いするのは密かな楽しみでもあります。

何度かの打ち合わせの後、いよいよ型取り、仕上げの作業を経て完成品を納品して頂きました。


最初にイメージした通り、木皮そのままの「耳つき絵馬」、ついにカタチになってきました。
写真ではなかなか伝わりづらいのですが、すいつくようなしっとりとしたきめ細やかな木肌なんです。面取りや穴あけなど細部まで本当に綺麗に仕上げて頂きました。
手に取ると、きちんと手間をかけていただいたことが肌から伝わる素晴らしい仕上がりです。またも想像以上の中嶋木工さんのお仕事に、こちらもテンションが上がります。

次回はいよいよ絵付けをしていきます。
今年の干支、龍のデザインは我が大村氏が誇る書道家 佐藤鳳水先生にお願いします。
完成が本当に楽しみです。
一本の木から絵馬ができるまで②
何とかなるだろうと思っていた製材でしたが、いきなり「絵馬を作りたいので丸太を持ち込みさせて下さい」と言っても中々良いお返事を頂けるはずもありません。見通しが甘かったことに反省しつつ方々にご相談した結果、最後に受け入れてくださったのが「長崎山陽株式会社」さんでした。突然の変なお願いにも関わらず快く対応して下さいました。
作業場につくと見た事もないような大きな機械が並んでいます。職人さんの慣れた手捌きでみるみる準備が整って、丸太が回転する巨大なチェーンソーによって割かれていきます。

厚さ20mm程に割かれた槙の木の板が約40枚ほど取ることが出来ました。
槙の木は建材としては天井材や床材、また桶などに用いられるように木目も美しく、耐水性にも優れています。なんとも贅沢な絵馬ができるのではないかと完成が楽しみです。
一本の木から絵馬ができるまで①

昨年の5月末、兼務神社の総代さんから「境内の木を切るのでお祓いをして欲しい」という電話がありました。大地や草木に神性を見出す神道ですから、出来うる限り境内の木は切らない。長く生きている木ならなおさらというのが常ですが、盛り上がった根っこが石柱を持ち上げて今にも倒してしまいそう。いよいよ見過ごせない状況になってしまったので総代さんとお話し、残念ながら伐採することに。

植木屋さんが作業に入る前に長年この地に生きた木霊を鎮め、大地に報告をする<木伐祭>を行い、この槙の木(まきのき)を伐採する運びとなりました。
年に数度このような依頼が神社にありますが、毎回私たちよりも大先輩の木を切る機会に立ちあうと少し申し訳ないような、寂しいような気持ちになります。ですが、だからこそ神主を招いてお祓いをするという日本人の美しい自然観が見て取れる機会でもあります。
事情があるにせよ、人間の都合で切ってしまうこの木を何かに使うことが出来ないかと数日ぼんやりと考えていると、ふと閃いて、参拝者の祈りを留める絵馬にしてはどうだろうか。それもただの絵馬ではなくて、木材の端のミミと呼ばれる部分も残して、よりこの絵馬が一本の木から作られていることを感じてもらえるような絵馬。
また日本人は語呂を大事にする慣習もありますので、神様に「願いを聞いてもらう耳」と、「材木の端のミミ」をかけてみてはどうかと思いつきます。
さて、どんなものが出来るか。伐採した材木の一部をもらい受けて製材所に持ち込み絵馬作りの始まりです。
制作の様子を引き続きご紹介してまいりますのでご笑覧頂ければ幸いです。
